《弹珠汽水瓶里的千岁同学》第七卷超长后记(生)(7)
それが最後の引き金になったんだろう。
夕方のランニングから帰ってきたとき、僕はもう一文字も書けなくなっていた。
頭のなかはぐるぐるとした焦燥感にどろりと黒い不安が渦巻いて、なにひとつ言葉が浮かんでこない。キーボードに手をのせたら冗談みたいにかたかたと震え始めた。いつもならとっくにクールダウンしているはずなのに、まるで走っている最中のように呼吸が浅い。
もう書きたくない、書くのが怖い、と初めてそう思った。
僕が自分の手でチラムネをだいなしにしてしまうという確信があった。
──ああ、もうここまでだ。
岩浅さんに連絡して発売を無期限に延ばそう。
デビューしてからこれまで、あまりにも一途に走り続けた。
半年ぐらいゆっくりと休んでからまた歩き出せばいい。
半分本気、半分朦朧として思いながら、それでも僕の手はスマホで検索を始めていた。
「不安 市販 薬 漢方」
毎日書くことは毎日走ることに似ていると思う。
一度でも「今日はいいや」と立ち止まってしまったら、二度と走り出せなくなる気がする。
だから「今回はいいや」と諦めてしまったら、きっと僕は二度と僕の好きなチラムネを書けなくなってしまう。
ドラッグストアへ向かうため、知らずのうちに胸を押さえながら車に乗り込んだ。
念のために断っておくけれど、僕はこれまで自他ともに認めるメンタルが強い人間で、もちろん心の不調を薬で誤魔化そうとするなんて生まれて初めての経験だった。
エンジンをかけ、せめてもの気分転換になればと窓を全開にした。
Bluetoothで車のオーディオと繫いだスマホを全曲ランダム再生にして音量を上げる。
あたりはすっかり夕暮れに差しかかっていた。
車を走らせながら、窓から吹き込んでくる風に吹かれながら、もう少し踏ん張るのかここで足を止めるのか何度も何度も自問自答した。あとなにかひとつ、たとえばドラッグストアでお目当ての薬や漢方が見つからなかっただけで、ぽっきりと心が折れてしまう予感があった。
そうして、道中の陸橋に差しかかる。
西の空が真っ赤に焼けていた。
そのときふと、スピーカーから流れる曲の歌詞が心に触れた。
夕方のランニングから帰ってきたとき、僕はもう一文字も書けなくなっていた。
頭のなかはぐるぐるとした焦燥感にどろりと黒い不安が渦巻いて、なにひとつ言葉が浮かんでこない。キーボードに手をのせたら冗談みたいにかたかたと震え始めた。いつもならとっくにクールダウンしているはずなのに、まるで走っている最中のように呼吸が浅い。
もう書きたくない、書くのが怖い、と初めてそう思った。
僕が自分の手でチラムネをだいなしにしてしまうという確信があった。
──ああ、もうここまでだ。
岩浅さんに連絡して発売を無期限に延ばそう。
デビューしてからこれまで、あまりにも一途に走り続けた。
半年ぐらいゆっくりと休んでからまた歩き出せばいい。
半分本気、半分朦朧として思いながら、それでも僕の手はスマホで検索を始めていた。
「不安 市販 薬 漢方」
毎日書くことは毎日走ることに似ていると思う。
一度でも「今日はいいや」と立ち止まってしまったら、二度と走り出せなくなる気がする。

だから「今回はいいや」と諦めてしまったら、きっと僕は二度と僕の好きなチラムネを書けなくなってしまう。
ドラッグストアへ向かうため、知らずのうちに胸を押さえながら車に乗り込んだ。
念のために断っておくけれど、僕はこれまで自他ともに認めるメンタルが強い人間で、もちろん心の不調を薬で誤魔化そうとするなんて生まれて初めての経験だった。
エンジンをかけ、せめてもの気分転換になればと窓を全開にした。
Bluetoothで車のオーディオと繫いだスマホを全曲ランダム再生にして音量を上げる。
あたりはすっかり夕暮れに差しかかっていた。
車を走らせながら、窓から吹き込んでくる風に吹かれながら、もう少し踏ん張るのかここで足を止めるのか何度も何度も自問自答した。あとなにかひとつ、たとえばドラッグストアでお目当ての薬や漢方が見つからなかっただけで、ぽっきりと心が折れてしまう予感があった。
そうして、道中の陸橋に差しかかる。
西の空が真っ赤に焼けていた。
そのときふと、スピーカーから流れる曲の歌詞が心に触れた。
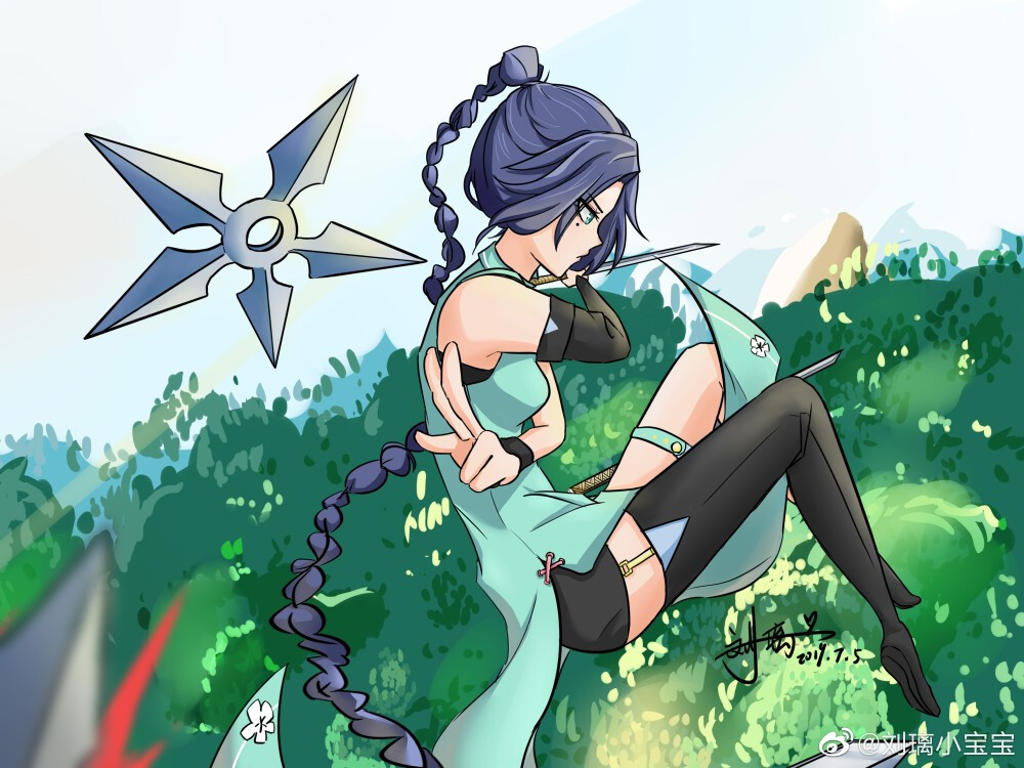
 学长的手指在里面转动的写作
学长的手指在里面转动的写作






































