第一章 『怒涛の一日目』 プロローグ 『始まりの余熱』(3)
2023-11-01 来源:百合文库
誰かがいるのだ。そしてその誰かがおそらく、自分を殺したのだろう。
不思議と、その相手の顔を拝んでやろうという気にはならなかった。
自分を殺すような相手、そんな相手にすら傍観を決め込むほど日和見主義だった記憶はないのだが、心はその相手の素姓など欠片も興味を払っていない。
ただ願ったのは――彼女が無事でありますように、ということだけだった。
「――バル?」
鈴の音のような声が聞こえた気がする。
どこが耳でどこが鼻かもわからない状態だから、空耳の可能性の方が高い。
それなのに、記憶を頼りに再現したのだとしても、その声はひどく心地よく感情を揺さぶる。
だから――、
「――っ!」
短い悲鳴が上がって、血の絨毯が新たな参加者を歓迎する。
倒れ込んだ体はすぐ傍らに、そしてそこにはだらしなく伸びた自分の腕があった。
力なく落ちたその白い手と、血まみれの自分の手が絡む。
全ては偶然だったのだろう。
かすかに動いた指先が、自分の手を握り返したような気がした。
「……っていろ」
遠ざかる意識の首根っこを引っ掴み、無理やりに振り向かせて時間を稼ぐ。
不思議と、その相手の顔を拝んでやろうという気にはならなかった。
自分を殺すような相手、そんな相手にすら傍観を決め込むほど日和見主義だった記憶はないのだが、心はその相手の素姓など欠片も興味を払っていない。
ただ願ったのは――彼女が無事でありますように、ということだけだった。
「――バル?」
鈴の音のような声が聞こえた気がする。
どこが耳でどこが鼻かもわからない状態だから、空耳の可能性の方が高い。
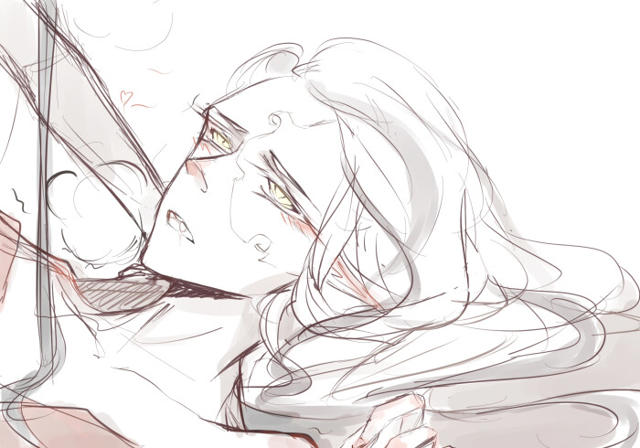
それなのに、記憶を頼りに再現したのだとしても、その声はひどく心地よく感情を揺さぶる。
だから――、
「――っ!」
短い悲鳴が上がって、血の絨毯が新たな参加者を歓迎する。
倒れ込んだ体はすぐ傍らに、そしてそこにはだらしなく伸びた自分の腕があった。
力なく落ちたその白い手と、血まみれの自分の手が絡む。
全ては偶然だったのだろう。
かすかに動いた指先が、自分の手を握り返したような気がした。
「……っていろ」
遠ざかる意識の首根っこを引っ掴み、無理やりに振り向かせて時間を稼ぐ。

 明日方舟斯卡蒂のェロ
明日方舟斯卡蒂のェロ




![[プロセカ│同人文] 流浪者,以及她的歸宿](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/0601/171251_17014.jpg)
![[プロセカ│同人文] 流浪者,以及她的歸宿](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/1025/154403_57048.jpg)
![[プロセカ│同人文] 流浪者,以及她的歸宿](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2023/0313/100855_93420.jpg)
![[プロセカ│同人文] 流浪者,以及她的歸宿](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2023/0313/103513_11950.jpg)







](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2021/1023/212703_77132.jpg)
](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/1123/104156_69983.jpg)
](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2023/0220/112414_51274.jpg)
](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2023/0322/152042_65860.jpg)
![オーバーロード15 半森妖精の神人[上]特装版(OVERLORD 不死者之王)](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/0408/154324_15951.jpg)
![オーバーロード15 半森妖精の神人[上]特装版(OVERLORD 不死者之王)](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/0525/165922_59124.jpg)
![オーバーロード15 半森妖精の神人[上]特装版(OVERLORD 不死者之王)](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/0613/174745_19022.jpg)
![オーバーロード15 半森妖精の神人[上]特装版(OVERLORD 不死者之王)](https://wimgs.ssjz8.com/thumbnail/2022/1025/154409_547335.jpg)








